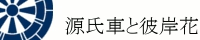銀の魔術師と妖精死譚
spinoff-妖音-妖音は書庫に誰もいないことを知り、奥の机に向かった。
別に何か目的があるわけではない。机についたら手足を投げ出して突っ伏して思考をする程度だ。
ひとつ、あくびをした。
机に出しっぱなしになっている本――法書、人事記録、史書などを見て、妖音はくく……と笑った。
どいつもこいつも真面目なことで。
まあ、こんな果ての先にある世でおもしろおかしく暮らしていけるのなんて、数える程度にしかいないのだから当然か。
かくいう妖音も、毎日がまったくおもしろくないクチだ。面白くないから周りを笑って時間を潰している。
夏葵は態度が露骨すぎるから、絡んでいて楽しい。
ああ、そういえば、来るなと言っていたな。さて、どうしたものか。
妖音は突っ伏したまま一人ほくそ笑んだ。
今まで夏葵で遊び過ぎたかとつらつら考えていると、懐でがさりと紙が擦れた。
そういえば、陛下から預かった手紙をポケットに入れたままにしていた。
鬼門の扉に腐食が広がっていることから書きはじめられた、原始の八咫鴉からの手紙だ。
妖音は伸びをしがてらに立ち上がると、書架の一つに向かった。
「妖怪学……生成り学……眷属学……ああ、これか」
妖精学と背に書かれた本を2冊抜き出す。
それを机にぽーんと投げ出す。
鬼門の扉の材質はわからない。もともとカビだ苔だとついてはいたが、腐るほどではなかった。
それを急速に腐らせたのは、此度の武藤斎についた妖精たちではないか。
妖音はそう踏んでいる。
どこか1箇所でも腐り落ち、穴が開いてしまえば、武藤斎の望みは達成させる。というか、一番簡単に武藤斎の望みをかなえる方法は鬼門の破壊だ。
残念なことに、あちらから鬼門を壊すという方法は取れなかったようだが――。
それに、武藤斎と妖精がやったという証拠になりうるものがもう一つ。
武藤斎が斃れたあの日、彼岸のあちこちで突然、あまりに多すぎる妖精の死が確認された。
それこそ、妖精の骸で山二つは築けるほどの数が。
その数、実に数千に及ぶ。
そのうちの半分は、鬼門の半径100メートル以内である。
どこにこんなに潜んでいたのか、感心するやら呆れるやらだ。
――そんなことはどうでもいい。
問題は、誰がその指揮を執っていたのか。あるいは、指揮とは言わずともその行動を起こさせたのか。
武藤斎ではありえない。彼女が川を越えて行き来することはできないからだ。
ならば、妖精か。
妖音はそう思って本を引っ張り出した。調べものなど数十年以来である。
ぱらぱらとページをめくり、妖精が彼岸-此岸間を行き来できるという記述や項を探すが――ない。
だとすると、やはり。
妖音は再び机に突っ伏した。本をぱらぱらとめくっては離して玩ぶ。
あちらとこちらを行き来できる者が妖精を煽ったとしか考えられない。
今、彼岸-此岸間を行き来する仕事をしていのは妖音一人だ。
また、原始の八咫鴉はその気さえ起こせば行き来できるはずだ。
それから、全ての特権を与える役を持つ陛下。だが世俗にまったく興味を抱かない陛下が、彼岸を揺るがすことをするはずはない。
だとすると、やはり。
妖音は出しっぱなしになっていた人事記録に手を伸ばした。
役も特権も取り上げられているが、除籍はされていなかったはずだ。それならば、このどこかにあの名前が載っている。
妖音は突っ伏したままページを確認していく。
夏葵から伝え聞いた仮面の男……この彼岸で仮面を常時身に着けている男なんて2人しかいない。
一人はこの彼岸唯一の永久凍土の引きこもり。もう一人は、もう何百年も行方がしれない。
妖音は手を止めた。
最後のページに補足注記として載っていた。
その容貌は目に火を宿し、人に相対す時は常に仮面をかぶりたる男。
妖音は確信を持っていた。武藤斎に近づき、しばしの暇つぶしとストレスをもたらしたのは、この男だ、と。
妖音はまたあくびをした。
その背後に人の気配がした。だれか書庫に入ってきたようだ。
「人に仕事をさせておいてこんなところでサボりとはいい身分ですね」
穏やかなようで冷ややかな声が背中に掛けられる。
直後、背後から本の山がなだれ落ちてきた。
「ああ、すみません」
「お前、悪いと思ってないだろ?」
「いえ、そんなことは決して」
妖音が肩越しに視線を投げると、そこには三つ編みをした少年が背を向けて本を書架に戻していた。
どう考えても妖音の背に落ちてくるはずのない本が雪崩れてきたのは、こいつの仕業だ。
ふと妖音は口元に笑みを宿した。
こいつは俺が仕事をしないで、自分のところに回ってくるのが気に入らないのだ。なら、最初からこいつの仕事にしてしまえばいい。
夏葵に担当を変えろと言われていたから、それもこいつにすればいい。
その上で妖音はこの仮面を追いかければ丸く収まるではないか。
そもそも他人の都合などどうでもいいが、これは妙案と思い、妖音は立ち上がった。
そのまま書庫を出る。出しっぱなしの本はあいつが片付けるだろう。
さて、この時間帯には陛下は何処にいらっしゃるか。
廊下を歩きながら、妖音は久々に愉快な気分になって笑った。