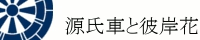銀の魔術師と妖精死譚
10.エピローグ「夏葵、機嫌悪いなら帰ってくれよ……」
「…………手数が足りないんだろう」
「確かに足りないけどさ……」
利はげんなりした表情で箱を床におろした。
夏葵は低気圧状態で年末年始の準備を手伝っている。
機嫌が悪いわけは、あかりが矢島に貸し出し中だからだ。協力の代償として今日を指定してきたらしい。
矢島もいい度胸をしていると、利はため息を吐いた。
正直このタイミングで引っ張られると、神社の方もてんてこ舞いなのだが。
夏葵もそれを知っているので、香葵を連れて手伝いに来てくれたのだ。
だが、その夏葵が低気圧。
利は再びため息を吐きかけて、ふと思い当たった疑問を口にした。
「夏葵、そういえば人形はどうなったんだ?」
妖音に引き渡すと言って、その時は終わりになったが、結局あれはどうなったのだろう。
「さあ……あれ以降会ってない。会いたくもないけど」
夏葵は絵馬の収められた箱を次々と重ねていく。
「なあ夏葵、お前あの妖音って男嫌いなの?」
「大嫌いだ」
「矢島とどっちが嫌い?」
夏葵は苦虫をかみつぶしたような顔をした。
「どっちも殺意が湧くほど嫌いだ」
しばらく夏葵はその顔のまま作業をしていたが、ふと素に戻り、数秒動きを止めた。
「どうした?」
「いや、……なんでもない」
帰り道、夏葵は香葵を先に帰らせると、一度学校の方へ足を向けた。
一本脇に逸れた道はどこか薄暗い上、曇天の夕暮れではもう闇に沈んでいる。
「くく……来たか」
「お前がわざわざ気配を残したから来たんだ。用が無いなら帰る」
「たいした用はないな」
夏葵は一つ舌打ちをすると、くるりと背を向けた。時間の無駄だ。
「あのあと、彼岸で妖精が大量に蒸発したぞ」
夏葵は振り返らずに眉をひそめた。
「武藤斎か」
「かもしれないなぁ」
「人形はどうした」
「どうにかなったんじゃないか?」
妖音の声は、実にどうでもいいと言いたげだ。
「仮面の男は」
「犯人探しだなぁ」
これ以上聞いても無駄だ。夏葵が無用にイラつくだけだから。
そう思い、夏葵はすたすたと道を戻り始める。
「そうそう、夏葵」
「…………今度は何だ」
「次からは俺の部下が来る」
「ほう、そうか。それはありがたい」
お前ほど根性が腐ってないことを祈るよ。
夏葵はそういうと、武藤斎が斃れ、妖音が立っているところへ後ろ手に手を振った。
空からはまた雪が舞い降りていた。