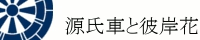銀の魔術師と妖精死譚
9.不死者は語る 02明りをつけなくても、雪明りでダイニングはほの明るかった。
唯一灯っているのは、奥のキッチンライトだけである。
夏葵はカーテンをひいていない窓に向かって膝を抱えた。
降り始めてから1時間もたっていないのに、もう外は真白に染まっている。
「ほい」
「ん……」
先までキッチンに立っていた利が、マグを夏葵に差し出した。そのまま傍らに座り込む。
香葵はソファに、家主のあかりはテーブルに掛けている。
「なあ夏葵、武藤斎の言葉って、どこまでが本当だと思う」
ぼそりと口を開いた利を、夏葵は一瞥した。
その目は明後日の方向――いや、神社の方向に向いている。
「神社のことか?」
「…………」
「どうだろうな」
利がわからない狭霧神社のことを、夏葵が知るわけがない。
利も、本当に答えを求めて尋ねているふうでもなかった。
「やっぱりあの伝えは本当……なのかな。だとしたら、うちの神社には本当に、神はいないのかな……」
利は夏葵には応えず、ひとり呟く。
そうは見えなくとも、武藤斎の発言に影響されたのか。
それとも、本当に訊きたいことは――
「……何だ?」
「あ、いや……夏葵、お前……」
利はそのまま言葉を失ったように、黙り込んだ。
何を訊いていいのかわからない。
何と訊いたらいいのかわからない。
利が言葉を詰まらせたのは、そんな気がした。
夏葵も、どう口を開けばいいのかわからない。
立てた片膝に、夏葵は顔を押し付けた。
しばらくの沈黙が落ちる。
誰かが身じろぎする気配が、嫌に大きく感じた。
ぎっ……と、椅子の脚が床を擦る音。
続くため息に夏葵が視線を向けると、あかりが髪を引っ掻き回しながら立ち上がっていた。
そのままキッチンに入るところで、ぽつりと言った。
「別に、訊かなくてもいいんじゃないの、利」
静かだが、その声はしっかりしている。
「あかり……」
「夏葵は、夏葵。そうでしょ」
あかりは急須に湯を注いでいる。
その表情は見えない。
「お前は、それでいいのか」
「いいも何も」
あかりがちらりと夏葵を振り返った。
顔には何の表情もない、いつものあかりだ。
「言ったでしょ。知らないといけない時が来たなら、否が応にも知ることになるって。わたしは、わざわざ詮索しようと思わない。それでも話したいというなら、聴くわ」
「…………いや」
そういってくれるなら。
何から話せばいいか、夏葵にもわからないのに。
夏葵の背後で、香葵のスマートホンが鳴った。