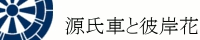銀の魔術師と還りし人々
18.霊視者 03「二人ともおかえり」
「ただいまー慧兄。悪いけど居間も借りるねー」
「うっかり壊したりしないでね」
慧は縁側に陣取るとひらひらと手を降り、煙草を咥えた。
居間ではふてている夏葵が寝ている。
香葵は花衣と紅衣の相手をさせられていた。
「花、紅、お前らちょっと外してろ。外に兄貴いるから」
「はーい」
香葵を解放して走り去るのを認め、利はカーテンを引いた。
慧には悪いが話しにくい。
「さてと、夏葵はどうする」
「放っておけば?」
投げ出した鞄は手に届くだろう距離で、隠す様子もなくナイフが覗いている。
あれはふてているだけで寝ていない。
「……何?」
「あ、俺が訊きたいことあって駄々こねたの」
「ま、その前に確認事項がいくつかあるけどな」
どこかに行っていたあかりが戻ってくる。
誰対策に木刀を持ってきたのか謎だ。
「矢島、あんたが魔術師でなければ、あんたは何なの?」
あかりが訊いたのは答えさせるためだ。
おそらくあかりが訊くのが一番穏便に進む。
「……なんて答えたらいいんだろうなあ。見鬼……かな」
「――見鬼だ?」
古代中国の道教思想を取り入れた日本陰陽道で鬼や怪異を見るという先天的な才。
それを持つ、者。
「生まれつきね、見える。写真やテレビデオ映像が本来のものだとしたら、俺の目に映る現実は一致しない」
「生まれつき?」
「そう、子供の時に気が付いて言わなくなっただけ。俺にしか見えてないってこと。視力が落ちてからより見えるようになっただけ」
矢島はあかりに喋っている。他には視線を向けていないことからそれがわかる。
いっそすがすがしいほどに。
「ていうことは、魔獣だけじゃなくて花や紅も見えてたってことね」
「あ……」
「うん。いつもは年末くらいしか見かけなかったけど」
利は当たり前のように声をかけたが、見えない人がそれを見たらさぞかし変だったろう。
「てことは、下手すると俺らが見えてない奴らも見えてるってことか」
「多分。でも俺に見えるのは本来、呪力の流れ。湧きや澱み、障害があると流れが変わる。水がそうでしょ?」
「待て。呪力の流れが見えてる?」
「うん」
利の静止に、矢島は当たり前のように頷いた。
「――霊視者」
「霊視……?」
「矢島、親は見えるの」
「流れ? 多分見えてない」
突然変異種か。
「じゃあ、俺の呪力体質も見たってこと……?」