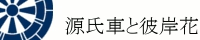銀の魔術師と捕縛の糸
14.学校に隠れるモノ 01「夏葵、それ何?」
「ん?」
夏葵は顔を上げた。
昼休みになったばかりの教室である。
夏葵は本を持ちあげて、背表紙をあかりに向けた。それを見たあかりの顔が呆れる。
「……また」
魔道書か、と後半を飲み込む。
「授業中何読みふけってるかと思ったら、まったく」
「それで当てられて答えられるとか羨ましい奴だなオイ」
「浅井、それ生物だからだろう?」
夏葵は本を閉じた。首を回す。
「とはいっても、中学の復習だろ」
「……なんで毎日毎日そんなもん読んでるんだ」
無理やり話題変えたわね、とあかりが笑う。
「仕返し」
「お、やるんだ?」
あかりが楽しいいたずらでも見つけたように笑う。
「当たり前。身を以って後悔させてやる」
とんでもない奴だな、と利が呟く。
「それで、相手は?」
「土蜘蛛――小田原」
いいねえ、とあかりはさらに笑う。
「と、1年女子に一人」
「誰?」
「名前は知らない。進学科C組、セミロングの女子。魔術で喧嘩売ってきた」
それは半月ほど前――4月の中旬から下旬に移ろうかという時だ。
ちょうど、各部が新入生勧誘に躍起になっている時期でもある。
客寄せのために、連日、放課後20分から30分生徒会室に立ち寄る羽目になっていた夏葵は、部屋の奥で黙々と本を読んでいた。
イヤホンで音楽でも聞いていれば、話も聞こえなくて苦にはならない。鬱陶しいのは視線くらいだった。
――俺は珍獣か何かか。上野のパンダか。立ち上がるレッサーパンダか。
内心うんざりしていた時、ふと、好奇その他諸々の視線とは別種のものに気がついた。
冷気をまとった視線――否、微かな敵意。
今度はなんだ、と思った。視線の質からして小田原ではないくらいに小田原には睨まれている。
夏葵は一つため息をついて顔を上げた。途端に黄色い声が上がる。
夏葵の目はそれを通り過ぎ、出入り口――廊下に向けられた。
半ば確信していた。
いる、と。
廊下にまで群がっている野次馬に目を眇めた時、そのうちの一人が離れて行ったのを夏葵は確認した。同時に視線がかき消える。
――あいつか。
顔までは確認できなかった。その時は。
その後に、夏葵のいう、「喧嘩を売ってきた」事件があったのである。