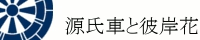銀の魔術師と捕縛の糸
13.桜吹雪に隠れるモノ 04翌日、小田原は眉間にしわを刻んだまま入学式に臨んだ。
「小田原先生、その表情、まずいですよ」
隣に座る生沼が気弱な表情そのままに、気弱な声で注意してくる。
小田原は軽く顎を引くと、何でもないように無表情を取り繕った。
そのうちは、今も感じる異質感を気にしている。
凪夏葵が動いているように見えない、ということは有害ではないのか。それとも凪夏葵が何かしたのか。
――わからない。
再び、眉間にしわが刻まれかける。
それも、主任がマイクの前に立ったことで引きとめられた。
アナウンスの後、進学科の新入生が入場してくる。
彼はそのうちのひとりに目をとめた。
無表情に口を引き結び、セミロングの髪を後ろで軽く結んでいる。
淡々と、粛々と、式典は進む。
入場、着席、点呼。
新入生が次々と起立する。
小田原は僅かに目を眇めた。
――山下、怜奈
夏葵はページをめくりかけた手を止めた。
受付案内の控室になっている、昇降口近くの教室の窓際だ。
「夏葵?」
差し向かいで雑誌をめくっていた香葵が不思議そうに目を向けてくる。
一瞬の違和感。香葵はそれに、いつものことながら気づいていないようだ。
あかりと利はいない。あの二人は協力要請を「バイト」の一言で突っぱねた。
「――なんだ?」
「何が?」
香葵じゃ話にならない。
夏葵は本を閉じて窓の外を睨んだ。
きれいに晴れあがった空に桜並木と花びらがよく映えている。
その桜の枝には、花を目隠しに何か居るような、そんな感じがした。
今はちょうど、進学科の入学式の真っ最中だ。頃合いからすると、点呼だろうか。
――点呼。
夏葵はそれが引っかかって瞬きをした。
名前を呼ばれて、返事をする。ただそれだけの行為だ。
だが――ありうる。
もしこの違和感の正体が魔術師によるものだったら、点呼だけでも可能性に含められる。
だとしたら、名前を呼ばれた瞬間だ。
――だれか来たのか。
全く無関係のものか、あるいは小田原の差し金か。
――知ったことじゃないか。
夏葵はそう開き直ると、本を開いた。
おそらく、この手の違和感は香葵やあかり――は予測不可能だが、利の場合は相当強く出るはずだ。
真っ向勝負の場合、それほど恐れるに値しない。このとき一番怖いのはあかりのようなタイプなのだから。