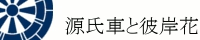銀の魔術師と捕縛の糸
10.浮上 01眩しかった。
手足は、皮膚の下に鉛を詰め込んだように重い。
何を思うでもなく、幾度も瞬きをした。
「んん……」
声が聞こえて、重たい頭を傾けた。それまでその存在にすら気付かなかった。
――香葵?
どうしてここに。
そこではじめて、あたたかいと思った。
自室のベッドだった。
いつの間に、という思いと、帰ってきた、という思いが交錯する。
「なつ、き……」
ベッドに突っ伏した香葵が小さく呻いた。
視線を上に戻すと、蛍光灯がつけっぱなしになっていた。
枕元には水差しが置かれていた。
微かに煙草の残り香がする。親父が居たのだろう。
寝入る気にならなかった。
部屋の中には時計の秒針の音と、香葵の寝息だけがあった。
しばらく付きまとっていた視線もなかった。
酷く静かで、酷く心地が良かった。
しばらくぼうっとしていたが、あかりと利がふと気になった。
そもそも、意識が飛んでから何があったのだろう。
そう思っていると、タイミング良くドアが開いた。
「……起きたのか」
顔をのぞかせたのは、くわえ煙草の健一だった。
部屋に入ってきた拍子に、煙草の先から細かい灰がこぼれた。
いつもなら言う文句も、面倒だった。
健一は椅子を引いてくると、大きく欠伸をした。
「さすがにこの歳にもなると徹夜は堪えるな」
「……寝ればいいだろ」
「まあそう言うな」
健一が手を伸ばしてきて、容赦なく髪をひっかきまわした。
「お前はどうも面倒事に巻き込まれるようだな」
「悪かったな」
夏葵は煙草臭い息から顔を背けて、目を閉じた。
「何があったんだ」
「んー、いちから話すと長いんだ」
「端的に言え」
「呪力の暴発、鎮静化、気絶」
健一は新たに煙草をくわえて即答した。
「身体が重いのは体力が底をついてるから。呪力はあるだろうけど、実用に耐えれるほどじゃない――夏、お前春休みに一回帰ってこい」
「は?何で」
「そのままだと身体が持たない」
健一はジッポーを弄びながら続けた。
「その能力(チカラ)は人の体には毒だ。お前が安定して使えるようになるまでは封印を続けていた方がいい。昨日の一件でタガが緩んでいる――放っておけば身の破滅だ」
「……わかった」
わかったよ、と夏葵は呟いて、布団を引っ張り上げた。