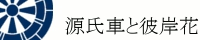銀の魔術師と孤独の影
10.エピローグあの後、休みを挟んでしまったため、あの魔術戦闘のことも宙ぶらりんのままで落ち着いてしまった。
たとえ気になることがあっても口に出しにくいし、もうどうでもいいような気がした。
だから、というわけではないが、放課後話しかけられても反応は鈍かった。
あれだけ騒いでいたあかりよりも利の方がよほど反応がいい。
とはいっても、
「へえ……」
話しかけられていきなり感嘆詞を言われるのは気分がいいわけではない。
「何?」
「いや……?」
あかりは視線を上げた。夏葵はあかりの席の斜め前で口元をかすかに歪めて――笑っているのだろうか。
「――何?」
今度は気分を害してそういうと夏葵は軽く顔をそむけてくつくつと笑った。
話かけられてわけも分からずに笑われるという、この反応はさすがに頭にくる。
物騒にも殴ってやろうか、という考えが浮かび拳を握ったところで夏葵は口を開いた。
「認めるよ」
「……は?」
「お前は魔術師だよ。最初はなめてたけど」
なめてたのか、という文句はとりあえず言わずに夏葵の言葉の続きを待った。
「たとえ最初から気付かなくったって――」
夏葵はすぐ傍の椅子を引いて腰を下ろした。
よく見れば、クラスには利のほかに人影もいない。
「途中から気付いてあれだけの対処が出来て、俺の行動を把握するために、魔術気配の決してない方法を使うんだから」
あかりは確信した。夏葵は笑っているのだ。そうとは見えないくらい不器用だが。
「……お褒め頂きありがとう。――最初に笑わなければ純粋にほめられた気がしたかもしれないけどね」
あかりがそういうと、夏葵はさらに笑った。さっきよりも自然に。
「それは悪かった。――魔術師に対して武力をもって対処――自分のバックアップまで用意して」
「――で? 何が言いたいの?」
「何も?」
「はぁ!?」
夏葵はまたひとしきり笑った。
そこであかりは気がついた。夏葵が笑ったのは、編入以来見た事がなかったことに。
「そうだね――強いて言うなら、気にいった、くらいのものかな」
「気にいったぁ?」
関連性が見えなくて見事に驚かされた。そもそもどこに夏葵に気に入られる要因があったのかが分からない。邪魔したせいで嫌われるならまだしも。
夏葵にとって話したいことは話終わったのか、椅子から立つ。
「まあ、もし俺が不得手な分野の仕事が回ってきたときは――あんたらを呼ぶよ」
その方が楽しそうだ、夏葵は今度こそ口元に笑みを浮かべて教室を出た。
「楽しそうって……」
ますます意味不明になってあかりは頬を掻いた。