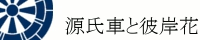神代回顧録
雛 02石段には、恐ろしく生き物の気配がなかった。
砂塵が積もっている石段は、長いこと誰も踏んでいないことがわかる。
それはそうだろう。少年の記憶が正しければ、里の者はずっと、外に出ていない。
石段の下から、誰かが上ってくる気配もない。
ただ石段と、ところどころに立っている石柱と、その合間を流れる霞だけが、そこに居座っている。
うっすらと遠目に見える木々だけが、年々存在感を増しているだけだ。
どうして誰も、この里から出ないのか。
どうして誰も、外に興味を持たないのか。
足元の小石を一つ拾うと、下方に放り投げた。
ひょうひょうと耳元で風が鳴り、小石はどこかに飛ばされてしまう。
ため息を吐いた。この何もない高所の里は、閉鎖的すぎる。
少年はふと耳を澄ますと振り返った。
呼ばれた。
「あかつきー、暁ー?」
「なあにー?」
人影を認めたところで少年――暁は声を返した。
こちらに駆けてくると、金の髪をなびかせた青年は、暁の頭をくしゃりと撫でた。
「なあに、じゃないだろう。そろそろ夕霧が出るころあいだ。早くムラに戻ろう」
「…………ん。ねえ真竹」
暁は立ち上がって尻を払いながらも、視線は石段の先に据えていた。
「真竹は、里の外に出たことある?」
「ない……けど、どうしてそんなことを聴くんだ?」
「何で出たことないの?」
真竹は怪訝そうな表情をした。暁の言っていることが理解できないという顔だ。
「何でって言われても……そもそもどうして里から出るんだ?」
話がかみ合わないように感じて、暁は頭をかいた。
「ほら、帰ろう。日が傾いてきた」
真竹は暁の背を押して、ムラへと歩き出した。
暁は押されるままに歩きながら、ひっそりと、2度目のため息を吐いた。
八咫鴉の住むこの里は、他の地から孤立しているせいで、なにかおかしい。
度が過ぎた閉鎖志向。
そのことにすら気が付かない仲間。
誰も彼も――暁以外は――疑問すら抱いていない、争いもない桃源郷。
その様子が、暁には不自然に思えてならなかった。
だって、他の神筋も異筋も、少なくとも争う形で余所の里と接しているじゃないか。
「今日は真竹のところにいていい?」
「だめって言っても、なんだかんだごねてついてくるんだろ?」
暁は頷いた。真竹より屁理屈を捏ねるのは得意だ。
真竹が苦笑する。それは駄々をこねる弟に、仕方ないという表情そのもの。
兄がいたら、本当に真竹のような存在かもしれない。
ふと真竹が険しい顔をした。視線を追うと、景色の端々に霞がかかり始めている。
本格的に急いだ方がいいかもしれない。
「真竹、競争しよう」
暁はするりと真竹の手から逃れると、一足先に駆けだした。
刈り入れの終わった畑のあぜ道を一直線に駆ける。
飛びたい、と思った。
このまま飛んでしまいたい。
里から飛び出したい。
その思いとは裏腹に、暁は真竹の住む小屋に飛び込んだ。