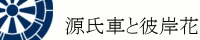彼岸花の咲く川で
3.卓のはなし 04「原始の八咫鴉、『大禍』で落ちたっての、知ってるだろう?でも蘇るほどの奴が落ちるとはちょっときな臭い。それで俺は調べてみた」
「調べてみた、って……」
新人研修のときに習った記憶が正しければ、原子の八咫鴉も『大禍』も禁書ではなかったか。
「お前それ、禁書……」
「まあそうだな。それでだ、調べて驚きの事実が発覚。――原始の八咫鴉は落ちたんじゃない。落ちに行ったんだ」
「落ちに行った?」
「そ、自分から彼岸の果てに行ったの。そもそもお前、『大禍』が何だか知ってるか?」
――『大禍』
それも基礎知識程度は知っている。
時折開くことはあるが、基本的には固く閉ざされた鬼門が綻び、あわや閉じなくなりかけた事件である。
閉じなくなりかけたのをどうやって閉じたのかは澪実の興味が向いたが、研修監督は決して言わなかった。
そのこと卓に言うと「やっぱりな」と答えた。
「ちなみに、建前上は彼岸の住人が力を合わせたことになってる」
「や、それはあり得ない」
澪実然り、卓然り、他の住人もそうだが、基本的には協調性のない連中の集まりである。共同作業などあり得ない。
「ま、所詮建前だしな。それで実体は、原始の八咫鴉が独力で鬼門を閉ざし続けているんだ。今も」
「嘘だろ?大ホラだろ?本当なわけないよな?本当だって言うなら、俺泡吹いて倒れるかもよ?」
「残念ながら史書ににそう書いてある」
「うっそだー!!!」
あのどでかい鬼門を一人で封じるなんてそれこそあり得ない!!
まず鬼門は上がどこまで続いているかわからない代物なのだ。見上げると上はかすんでいる。幅は澪実の船が二つ、厚さは澪実の腰回りほどある「力自慢が百人いても開かない」門である。
「詳しい話をするとだな、鬼門が開いたときに此岸にいた原始の八咫鴉が何か細工をしたらしく、滅びない自分の体を呪具にして封印を守っているとか。
そして封印を保ち続けるために人が踏み込むことのないようなところで今も全身全霊をかけているんだ」
「その細工ってなんだよ」
「読んでも理解できないことがずらずらと書いてあったから読みとばした。知りたいなら自分で調べろ」
ちなみにその人の踏み込まない所なんだが、と卓はグラスに酒を注ぎながら言う。
「彼岸の果て、といわれてきたが実際は彼岸の最下流域のさらに奥、『禁域』だって」
「『禁域』?」