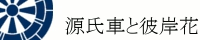夢殿
侵蝕屋 02夢を、見たんだ。
私はベッドに体を起して、やっとそうと気づいた。
あの場所は――そう――何もない闇の中。
茫洋とかすみが流れているから、風があることはわかった。
足元は暗くていまいち確認できない。
アスファルトではない。砂や草を踏む柔らかい感じとも違う。
前方には、弱い火の明かりが見えた。
その後ろには、さらに深い闇が――何かあると存在を主張している。
明るいところを目指して、私はそこへ近づいた。
建物から光がこぼれている。
その建物は、相当古そうだった。
作りが神社に似ている。あるいは、そう、歴史や古文の教科書に載っている木造の建物。
光の向こう――建物の中は光の気がないのか、さらに深く闇が口を開けている。
その中の闇の一部が揺らめいて、それは人となって現れた。
「いらっしゃい、お嬢さん」
低く静かな声がしたかと思うと、明かりの中で人の形を結んだ。
感情の読めない静かな表情に、かすかにゆるめた口元は笑っているのだろうか。
ぼさぼさの髪は伸ばしっぱなしで、格好は平安や貴族公家のそれ。
ただ、火に照らされた白い顔には生気がなかった。
人として、完結した気配――のようなものがある。
「ここは現世に在らずして心に扉有りし世界。生と死とともにありながら不可侵の夢。領域の陰の主にしてこの庵の主の世界へ、ようこそ」
その男の言ったことは、半分も理解できなかった。
「私は、『侵蝕屋』というものです」
その時、男は確かに笑った。
「その願い、叶えましょうか?」
その表情は、私の何にも響くことなく、感情を上滑りした。
最近の私の生活は憂鬱だ。学校生活が。
朝に昼休みに放課後に、私を含めた5人のグループにひっついて回る虫がいる。
一言で言うと、ウザい。あるいは空気が読めない奴
これは別に私の僻目じゃない。クラスやその虫を知っている人たちの総意を、最もありふれた表現にしただけだ。
この手の存在は持ち回り制が暗黙の了解だが、こいつは持ち回りされてくれない。
追い払っても追い払っても、一向にめげずに私たちに付いて歩く。
正しくは、私たちの聖女、マナについて離れない。
マナ、優しいもんなあ……。
心が狭くて口が悪い私とは、比べるのもおこがましいほどの人格だ。
そんなマナですら「あの子はちょっと……」というのだから、あいつは人間失格――いや、生命体として失格だと私は思う。
それが、今、私の目の前で弁当を食い散らかしている。
会話も空気も重い。
マナはどうしていいか困っている様子だ。
私とミーは対立派なので敵意殺気混じりの視線と空気を放っている。
完全に興味なしのレイは、ひとり何処を吹く風だ。
一時期べったりはりつかれていたノリは、離れることでぎりぎりの安寧を保っている。
楽しそうなのは、生物としての第六感が狂ったあいつくらいだ。それも、一方的に話すだけ。
何組の誰それ君がかっこいいだの、数学の誰先生は自分に皮肉ばっかり言ってくるだの。
――知らないよ。
私たちにとって、今、最大の懸案事項は――音だ。
どうやら口を閉じて物を食べることが出来ないらしい。
口を閉じて物を食え、と一度キレたが治っていない。まあ、一朝一夕に治ったらのけ者にされることもない――というのは言い過ぎか。
あいつの弁当は、残り半分と言ったところか。
「あ!そーだ。ねぇねぇ、誰か体育着貸してくれない?忘れちゃったぁ」
全員が無視した。誰が貸してやるもんか。
クラスが違うノリは体育着があるはずだが、サイズの違いを理由にいつも断っている。
私のクラスは昨日体育だったから、誰も持ってきているはずがない。まあ、私やミーに借りるわけもないのだが。
「ねぇ、ちょっとぉー」
甘ったれた鼻にかかる声に、私は口の中で舌打ちをした。不愉快だ。
「誰か貸せる状態の物はある?」
レイがひどく冷めた声でお義理のように問い掛けた。誰も返事をしない。
「えぇ~そんなぁー。あたしこの前も忘れてぇー、ちょっと出席ヤバそうでさぁ」
自己管理不足、ミーがぼそりとそう呟いた。
そもそも、こんなことは今に始まったことではない。教科書忘れた体育着忘れた予習見せてくれ課題見せてくれ。もうこりごりだ。
どうやら、物事には限度があると言う事をこいつは知らないらしい。
チャイムがなるまであと10分。その限度を超えないように私は祈るだけだ。
一回死んじゃえ、といつもそうするように、私は心の中で呟いた。