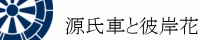銀の魔術師と妖精死譚
3.手紙 03「あーあ……」 ベッドに倒れ込んで慧は目元を覆った。
芳史。
伊勢本家。
神舞。
「…………面倒臭い」
嫌になる。
これだからしがらみは。これだから、上下関係は。
「神舞……か」
馬鹿らしい。枕に顔を押し付けた。
あかり……あかり……
「あかり!」
慧はほっと安堵の息を吐いた。
「ほんと、よかった……」 普段は人の住んでないあばら家には、今、芳史と慧がいた。少し前にはもうひとりいたが、帰ってしまった。
無表情のあかりは、慧のいる縁側を通り過ぎ、井戸のポンプに取りすがった。
錆びついた音を立てて、少しずつ動くそれは、まだ幼いあかりには重い。
「待て、出すよ」
「…………」
中にしまっている靴を取りに、慧は身を翻した。
その背中でガン、と不穏な音に続き、水が桶に注がれる音がする。
慌てて靴を履きながら戻ると、あかりは既に井戸水で顔を洗っていた。
桶に張られた水がみるみる赤く染まっていく。
手から、顔から、髪から、服から、落ちた血だ。
だが、いくら血が落ちようと、血脂までは取れない。
「あかり、石鹸いる?」
「……うん」
洗い場に置き去りにされた古い石鹸をあかりに放ると、濡れた手で器用に受け止める。
しかし泡立てているうちに、つるりと滑って足元の鉄パイプの横に落ちた。
ああ、あかりはあれで井戸のポンプを強打したか、輪に通して体重をかけたのか。
「もっと水出そうか」
「……うん」
石鹸を拾ったあかりが小さく頷く。
どこかぬるりと脂で滑る手押しポンプを掴み、慧は体重をかけた。
11歳の慧にも重いポンプを、7つのあかりはよく押したものだ。
――いや、それを言ったら、まず生きて帰ってきたことを驚くべきか。
汲み上げた水で無心に髪を洗うあかりをじっと見た。
「ああ、あかり、無事帰ってきたんだね。お疲れ様」
さっきまで家の中で寝ていた芳史が、起きて顔を見せた。髪に寝癖が付いている。
芳史は縁側に腰掛け、あかりが血糊を落とすのをぼんやりと眺めた。
「また盛大に被ったね」
「…………」
あかりは答えずに、濡れた髪を絞った。
服は諦めたのか、腕をまくると今度は放り出した刃物の手入れをはじめる。
慧はポンプを押すのをやめた。
「将来が楽しみで、怖いな。なあ慧?」
「……お前が言うか」
「今の俺には、家のことに口出しできないから」
慧も縁側に腰掛ける。
「あかりはうちから距離を置いて、実力を隠すことを覚えたほうがいいかもしれない。師範はもう知っちゃってるけど」
今であれだけの腕じゃん。この先どこから目をつけられるかわからないよ。
「……あかりは、」
「わかってるよ。家でしょ。まだ荒れてる?」
「当分収まりそうにない」
「……そうか」
芳史は胡坐をかいて、膝に頬杖をついた。
「あいつの姉ちゃんも、こっちのことは把握してるんだろ?」
「一応な」
「ここまで上り詰めてもなのか?」
「無駄だよ、みゆきには」
言ったって聞く耳も持たない。
いくらあかりでも、7歳と12歳の差は大きい。
ましてやあかりの姉、みゆきは、武芸、運動の天才。あかりは勝てた試しがない。
「上り詰めると、家は喜び子を褒め称え、敗者は血を吐きながら帰りて憎悪を燃やす……か。なのにあかりは、褒めてもらえない」
「師範か」
芳史が頷いた。
「褒められたことじゃないのにな」
こんな罪を背負わせるような行為。
呟く芳史の横顔を、慧はじっと見た。
俺たちが罪を背負うのならば、生まれる前から罪を背負っているこいつは……。
芳史が顔をあげた。視界の端であかりが刃物を振るい、きらりと光る。
手入れが終わったのか。
刃物を鞘に戻し、放り出していた石鹸を拾った。
「あかり」
「…………」
あかりは声をかけた芳史をいぶかしげに見た。何だ、と目が言っている。
「神舞、おめでとう」
「…………」
「祝福はしない」
「…………そう」
どちらも、そうとわかりきったやりとり。
ふいと土間に向かったあかりを見送り、芳史は腰を上げた。
「慧、狭霧神社に、一応手紙を出しておこう」