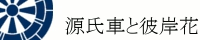夢殿
影繋ぎとん、
ぱらりとめくれたノートを拾おうと、床に手を伸ばした姿勢のまま私は固まった。
「5月9日 木曜日 くもり」
「5月10日 金曜日 はれ」
「5月11日 土曜日 はれ」
日付と天気だけが書かれたノートのページ。
おやと思い、ノートの表紙を見ると、そこには高校1年の冬から高校2年の秋までの日記とある。
ぱらぱらとページをめくると、2月3月の間はきちんと10行ほどの日記が書きつづられている。
それが4月の半ばからはどうだ。5行、3行と減り、4月末には日付と天気しか書かれていない。
首を傾げた。この差は一体何だ。
――高校2年。
一体何があっただろうか。
何だろう、声が聞こえる。
「あれがお姉ちゃん」
気がつけば、左手を少年に取られていた。
少年の向こうには、うつむき気味で表情の見えない、背格好が同じくらいの女の人。
「――誰?」
「お姉ちゃん、ほら、見なきゃ」
少年がそう言うと同時に、向こうで笑い声が弾けた。
きゃはははは、と耳に着く品のない笑い声。
「意味わかんなーい」
「ばっかじゃないの? あ、馬鹿かあ」
「ってことでこれ、わたしたちがもーらい。くれるんでしょ?」
ぞく、と背筋が泡立つ。
聞きたくない。本能が拒絶する。
騒がしい影がいなくなると、ぽつりとひとつだけ後ろ姿が残る。
やがてその影がふらりと歩き出す。
少年に手をひかれ、私たちも歩き出す。
影の前に扉が一枚現れる。
「美術室だ」
少年がそう言った。
からりと軽い音を立てて開いた先にあったのは、油絵の具の匂いが染みついた部屋。
そうだ、私は高校の時は美術部に……。
部屋の中には談笑する一団がある。
影が何か声をかけた。だが誰も返事も、見向きもしない。
一団から数歩離れたところに、ぽつりと立つ、影。
しばらく立ちつくしていた影は、ふらりと揺らぐように背を向けると、一つのキャンバスに向かった。
少年に連れられ、影の後ろに回る。キャンバスが見えた。
暗い。色彩が暗い。
どんよりと暗い空。それとも夜だろうか。
影が絵具を探してしばらく手を彷徨わせる。
絵具が一部欠けている。
影がしばらく動きを止めた。その後ろで弾ける笑い声。
影がうなだれた。
長くうなだれていたかと思うと、影はもたもたと動き出した。
白や黄色と言う明るい色を取り出し、細い筆に乗せる。
背後から、私たちを突きぬけて、影に向けて不可解そうな空気が突き立つ。
何をするつもりだと、ひそひそと声が聞こえる。
影はしばらく迷った様子を見せた後、少しずつ暗い背景に色を乗せ始めた。
やがてそれが、線を作り、形を作っていく。
「……夜景?」
それは、確かに夜景だった。だが、遠すぎる。
キャンバスは、あまりに暗い。
ふと、私はその絵に違和感を覚えた。
―――何だ、何だ?
「お姉ちゃん、よく見て。よく――――
見て。
はっとした。
目の前には、日記のノート。
少年も、女の人も、影もいない。
よく見ると、ノートには何度か消しゴムをかけて消した跡がある。
上から文字が重なってて、読むことはできないが。
よく見て。
頭の中で声がした。
促されるように、ノートに目を落とす。
ふと、指に違和感を感じた。紙がゴワゴワしている。
ゆっくりと紙を撫でると、ところどころに違和感がある。
しばらく見つめて、それが涙の跡だと気がついた。
脳内に不快な笑い声が蘇り消えていく。
嘲笑。
失笑。
冷笑。
次々と脳内に蘇る。
私はハッとして、ノートを放ると押入れを開いた。
いくつかしまい込んだキャンバスのひとつ。黒い、暗いキャンバス。遠くから見た、寂しい夜景の絵。
「あれは――」
あの影は、
「そう、私」
突然の声に、私はばっと振り返った。
私の後ろに、女の人が立っている。
いつしか、少年が私の手を握ってた。
「そう、お姉ちゃん」
そう言って、少年が笑った。
「やっと迷子のお姉ちゃんが戻ってきた」
迷子の、私?
首を傾げる。
私は、迷子だったの?
「そう、迷子だった。私が。一人取り残されて」
女の人が言う。
「私が?」
「私が」
「あなたは――私?」
「そう、私があなた」
女の人――いや、私が、私を試すようにじっと見つめてくる。
そして、ふっと揺らいだ。
私の足元に伸びた影に、すうと融けていく。
「…………」
少年が手を離した。
「もう迷子にならないでね、お姉さん」
いつしか手にしていた日記を、少年が手渡す。
日記には、文字が刻まれていた。
「……うん」
日記から顔をあげたとき、少年はどこにもいなかった。